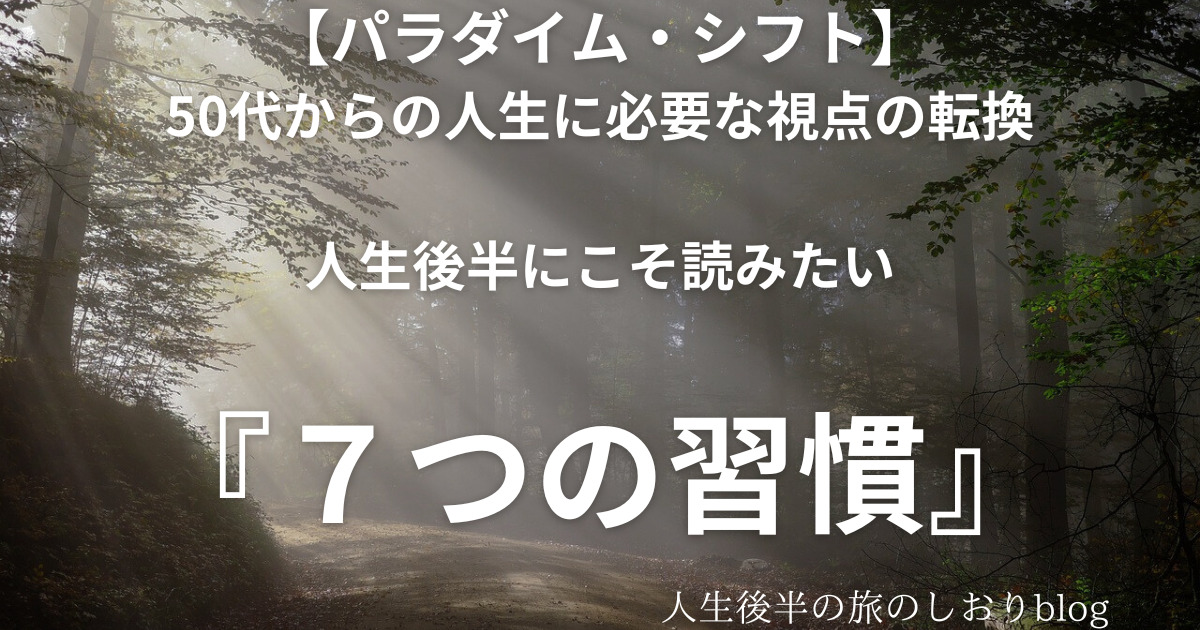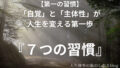50代の『7つの習慣』
世界的なベストセラー、スティーブン・R・コビィー氏の『七つの習慣』に接したのは大学の授業でだ。私が授業を受けるのではなく、この本を使って授業をするためだ。
その授業の講義名は「大学生活設計」というカリキュラムで、いかに大学生活や就職を設計していくかというものが講義内容となっている。特別な教材がなく、前任者が使用していたということもあって、『7つの習慣』を中心に大学生活に実践応用しようというものだ。授業の準備のために何度か読みこなしたり、『まんがと図解でわかる7つの習慣』さらに『7つの習慣ティーンズ』なども読むこととなった。
授業を進めながら、これを「私自身」に適応するのはどうか。さらに、50代からの生き方や習慣にも取り入れられるのではないかと思い始めた。一つの書籍を一度読んでおしまいというのではなく、何度も読み返したり、それを実践するように努めるということはめったにない。
もし手元になければ一度購入して一読することをおすすめする。ここでまず強調しているのは「自立」ということであった。私はほんとうに自立しているのだろうか。ここから私と「7つの習慣」との付き合いが始まった。
パラダイム・シフト
コビー氏は7つの習慣の項目に入る前の概要として「パラダイム・シフト」というテーマを提示する。書籍は翻訳されているから、日本語的な概念とマッチしないかもしれないが、まずは原書も念頭に置きながら、英語のニュアンスにも注意を払う必要がありそうだ。
「パラダイム」とはあまり聞きなれないが、要するに物の見方や考え方、認識、理解、特に今の私が常識だと思っている物の見方、考え方と言っていい。その見方が普遍的なものなのか、人生の原則に照らしての見方なのか。それとも、「私」の今までの生い立ち、文化的背景、教育、その時代の価値観などといった偏見で見ていることはないかというものだ。
よって、我々は時に「パラダイム」を変えてみる。つまり
「パラダイム・シフト」してみようというのが、この書の冒頭で主張していることである。
「パラダイム・シフト」
物の見方や考え方をシフトしてみようというのである。
私はメジャーリーガーの大谷選手のことをすぐさま思った。二刀流という概念。もちろん彼は二刀流ということは意識はしていなかったと思うが。
だれも考えもしなかったことを彼はやってのけた。最近は盗塁と本塁打の記録を積み重ね、記録を更新した。もしかしたら三刀流ではないだろうか。
だれもが考えなかった視点を持つこと。または異なった視点をもってそこから勉強や仕事を取り組んでみること。50代からの人生もこれに当てはめることで、新たな自分の価値を発見したり、人間関係が好転したり、さらに「生きがい」を持つことができないだろうか。と考えた。
ではどんな例があるだろうか。考え見てたい。
具体例
まずは自分自身に対する「パラダイム・シフト」はどうだろうか。
今まで自分自身のことを「こんな人間だ」「こんなスキルをもっている」「こんな経験をしてきた」という枠にとらわれずに、もしかしたら「こんなスキルにチャレンジしてみよう」とか「こんな得意分野があるのでは」と自分を見つめてみるという作業である。
コビィー氏はいう。正しく自分を磨きつつ、良心に耳を傾ければ、「内なる声」がそれを教えてくれると。
自分の内なるボイス
これに耳を傾けよというのである。ほんとにそうだろうか。一度試してみる価値はある。そのためには「パラダイム・シフト」をしようという意思や習慣が必要なのだ。
安定した仕事が一番だと思っていたが、自分の情熱にフォーカスし、転職や起業するというケースなどがそれにあたるであろう。
また、人間関係のとらえ方もここで応用できる。自分が長年「正しい」と思い込んでいた人に対して、視点を変えることで理解でき、人間関係が改善されていったというパターン。
『7つの習慣』ではまずは個人の習慣に集中する。主体的な人間になること、環境や周りに影響されず、逆に影響していく人間になる、そしてミッションステートメントという自分の憲法を決めるという作業。この段階が終わり、ようやく人とのコミュニケーションのスキルを磨いていく。
非常に明快で、そして自分の人生の課題に取り組むことができるような内容となっている。私が自立している人間になるということだ。
コビィー氏は健康や体力づくりにも言及している。健康についての「パラダイム・シフト」が起これば、健康や生活習慣も改善できるのである。確かに食生活は自身のライフスタイルであり、もっと言えば、自らの思考が食生活を決定しているといっても過言ではない。
これに関して、「7つの習慣ティーンズ」では、「自己信頼残高」という話しをしている。これは自分に対する信頼をどれだけ持っている、貯蓄しているか。というものだ。このためには、自分が決めたことや計画を達成し遂行することで高まってくる。
ダイエットや食生活も同じだ。自分のために、そして自分の信頼のために食生活を見直し、バランスの取れた生活を心がける。そして運動もする。これはまさに我々50代からの生き方に直結している指針だと思う。
影響の輪による主体性
コビィー氏はさらに、「主体的であれ」と第一の習慣で強調する。英語では「Be proactive」という。これは英語のニュアンスではより積極的であり、前もって対処し未然に問題を防ぐという意味だ。
我々は日々環境の中で生きている。職場、家庭、学校、組織。その中で自分が主体的に周りに影響を与えるというよりは影響されて、自分の主体性を発揮できてきないというのである。
そうなると、日々不平不満を言う、責任転換する、環境のせいにするという行動に出てしまう。
よって、自分の意志を中心に添えて、そこから周りに影響を与えていくという考え方がとても大切になっていくる。50代までは組織の中で自分を殺していたかもしれない。しかし、これからは、自分の意志を発信する、意見を述べる、自分の良心の声に従って自発的に生きていく。
こんな生き方はどうだろうか。それには「視点」を変えることが必要なのだ。
”私が私の人生を生きる”
とでもいえようか。これからの人生が面白くなってきそうではないか。チャレンジしてみる。やってみる。そして自分のやりたかったことをやってみる。これしかない。
人生後半の自立を目指して
さてそこで、「自立」ということがキーワードとなる。
主体的に生きることは、結局私が「自立」していなければならない。
今まで親や周りの人に支えられてきた。これはこれで感謝すること。ただ、いつも周りの意見や行動を中心に生きていないだろうか。人の目を気にしながら生きてはいないだろうか。
何を「中心」に生きているか。お金か、親か、上司か、食か、配偶者
「私の本来の思考」を中心に生きる。そのためには、
自らの考え、原則に沿って自分の考えや人生の目的を決める。これをしてみてはどうだろうか。
私もこの「7つの習慣」を実践したい。読者の方もぜひ一緒に実践ながら、お互い共有することができればお互いに成長し合い、シナジーを生み出せると思う。
真の自立を目指して、そして私の人生を生きてみませんか。
 | 完訳7つの習慣 30周年記念版 [ スティーブ・R.コヴィー ] 価格:2420円 |