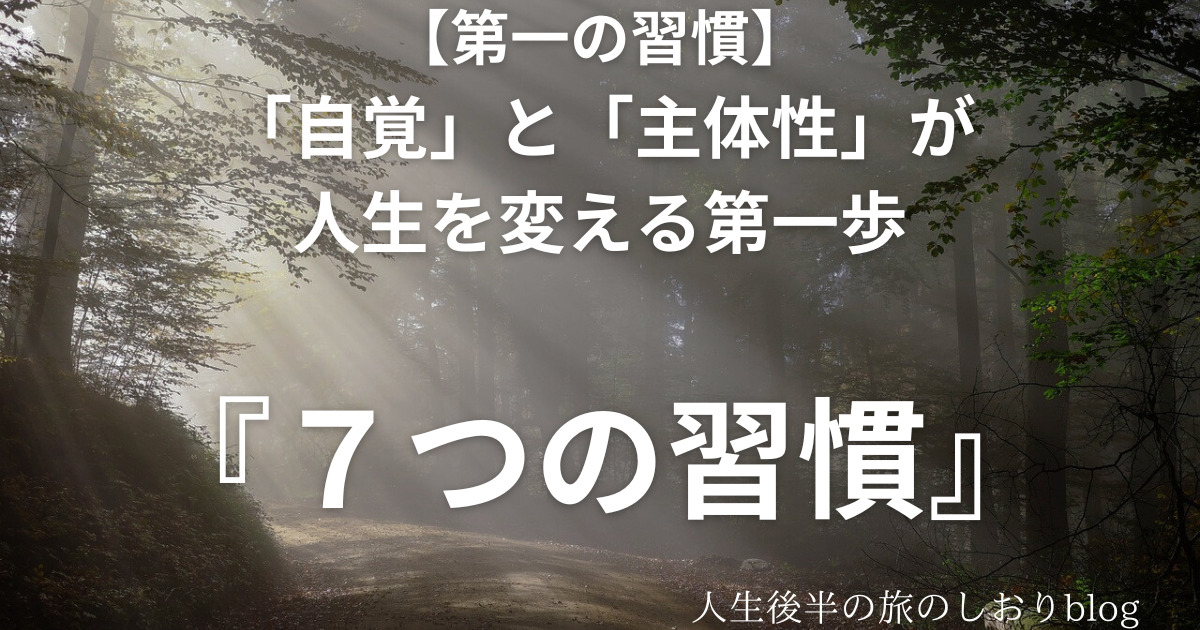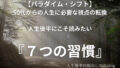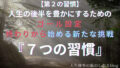今日は、「パラダイム・シフト」に引き続き、スティーブン・R・コヴィーの名著『7つの習慣』から、**第一の習慣「主体的である」**について書いてみたいと思う。
最近あらためてこの本を読み返す中で、「自分の人生をどう生きるか」という問いに正面から向き合う時間が増えたことは確かだ。つまり私はほんとうに自分の人生を生きているのかという問いだと思う。実際授業で使うこととなり、学生に伝えるというよりは、自分の今の人生に当てはめながら読み進めている。
特に心に残ったのが、“自覚”そして“主体性”というキーワードだった。
「自覚」といってもあまり普段意識しないものだ。
自覚は「~を自覚しているか」などと使われるが、「自覚」自体を意識して生活しているわけではない。英語では’self-awareness’であるが。この言葉に果たして我々日本人にピンとくるだろうか。
「自覚」つまり’自らを覚る’という意味なのであろうが、自らを客観的に見つめる行為。これをコビー氏は第一の習慣を理解するうえで冒頭に持ってきている。非常に重要なキーワードなのであろう。
最近「自覚」を意識しながら生活をしてみた。そのときに感じたのは、自分の感情や気持ちを冷静になって見つめてみるということだった。”今私はこんな感情を抱いているんだな。”というような感じである。その日は動物園に行ったのであるが、動物と人間を比較するということを念頭に考えてみた。何かと比較するということは、思索する上で有効な方法だとおもった。
さて我々はもう一度、この「自覚」ということを考えてみなければならないのではないか。つまり、自分を客観視すること。自分の言動がどのように日々なされているか。これは実際簡単なようで、非常に難しい。しかし、人間にしか備わっていないのが、この「自覚」なのだそうだ。
コビー氏は鏡の例を持ち出して、ゆがんだ鏡で見ていないか。本当の自分の姿をしっかり把握しているのかと問いている。ここでは日々我々は本来の自分の姿を見つめることの重要性を説いている。
親から言われた自分の姿、教師から言われた言葉の私の姿、思い違いの自分の姿。しかし、もう一度自分を見つめてみる。そして、私の本来の姿は何なのか。これを追求する価値はあると思う。特に人生後半を生きるシニアには必須かもしれない。
数日、この「自覚」を意識して生活してみるのはどうだろうか。私は学生にもこの「自覚」を意識して数日生活することを提案したみた。
そうすると、私自身の感覚であるが、自分を見つめる「もう一人の私がいる」「もう一人の私が私を観察している。」「私のことを見守り、リードしている」というような感覚を覚えると思う。
ではこのことと、第一の習慣である、「主体的」であれとはどのような関係をもつのであろうか。
「主体的である」とは何か?
そこで「主体的に生きる」とはどういうことをいう?
一度「主体的に生きる」という生き方を考えてみたい。
そんな中、思い出されることばとして
率先、行動力、積極性、前向きなどの言葉が挙げられる。
興味深いのは
コヴィー博士は、これを単なる「前向き思考」や「行動力」とは少し違う角度から捉えてるところだ。
それを理解する「キーワード」は、先ほど考えた
自覚
self-awareness
これは、自分の感情や思考、反応に気づく力。
そしてそれを客観的に見て、自分で選び直す力のことは先に確認した。
さて、ここからが問題だ。
「自覚」は、私たち人間だけが持つこの力であり、この力によって、「反応」ではなく「選択」ができるということなのである。単にある出来事が起きると、すぐに「反応」するのではなく、
「自覚」という能力があるがゆえに、我々には「選択」でっきる自由というものが与えられている。
つまり、
この「選択の自由」こそが、主体性の根本にあるとされるのだ。もう少し具体的に述べると、
「感情」を選ぶということ
なのである。感情はいろいろ湧いてくる。これに対して、すぐに喜怒哀楽をすぐに発したり、悩んだり、落ち込んだり、怒ったりするのではなく、
冷静に自分の原則と良心をつかって、判断するという過程を歩んでいくということなのだ。
みなさん
たとえばこんな経験はないだろうか?
- イライラしていた日の帰り道、つい家族にキツくあたってしまった
- 何かうまくいかないことがあると、すぐに「自分には無理」と決めつけてしまう
- 誰かの言葉に傷ついたり、気に障ることがあり、それが一日中頭から離れない
- 親にがみがみ言われて反抗してしまう
- 天気が悪いと、なぜか憂鬱になる。
- 不親切な店員に気分を害する。
私自身、こうした「感情に支配される日々」を何度も経験してきたように思う。こうした自分の感情に向き合うことは必要だ。素直に自分がどんなときにどんな感情を抱いたのかである。
でもそのとき、「自分はいま怒っている」と気づく“自覚”という作用があり、この”自覚”を活用しながら、自分を客観視する。そこから
もしかしたら平素とは違う反応や冷静な反応を“選ぶ”ことができたのかもしれないのだ。
自分で選ぶということ
コヴィー博士はこう言っている。
「刺激(出来事)と反応(行動)の間には、“選択の自由”がある」
ある行動や出来事が起こる。これに対してどう対処するのか。
まず、「刺激」を受ける。その次に、「反応」してしまいすぐに「行動」にでてしまう。しかし、この「刺激」と「反応」の間には自由がまだあるというのだ。感情に束縛されない。
われわれの自由。それはそこで「選択」できるというのである。
解釈や受け止めといってもいいだろうか。
「冷静」になってみる時間を持つ。そしてその次の行動をどのようにしていくか。ここからがもっと重要で、われわれの「良心」に照らしながら考えてみようというものだ。
もしすぐに反応を起こしてしまった、感情にただ振り回されてしまった、ということなら結局そこには「自分の主体性はない」つまり他人の意のままに自分が動かされているだけのことだろいえるのだ。
それは悲しいではないか。私を見失っている状況だ。反応してしまうということは、このような状況なのだろう。
しかしながら、実は私たちは状況や他人に振り回される存在ではないのだ。主体性のある個人として存在している。影響を与えられるのでなく、影響を与えなければならない。
そのためには
一歩立ち止まることで、「私はどうありたいか?」という問いに答えることができる。
そしてこの“選択”は、年齢に関係なく、今この瞬間からできることだと思う。いや経験を積んできたからこそ、自分の反応に対してよりよく選択ができるようになるともいえる。
40代、50代だからこそ、それが本当の意味を持つのだと私は思っている。
実生活でのパラダイムシフト:主体性を意識する実践
この「第一の習慣」です’主体的であれ’の習慣を、私自身の生活にどう実践しそして活かせるか?
コビィー氏が示した次の3つの実践を、まずは始めてみようと思う。
- 感情に流される前に、一度立ち止まる
→「今、自分は何を感じているか?」と内省する時間を1日5分でも持つ - 言い訳をやめて、“できること”を探す
→「忙しいからできない」を「どうすれば少しでも進められるか?」に言い換える - 使う言葉を変える
→「どうせ無理」ではなく「やってみよう」「選べる」といった主体的な言葉を意識する
まずは一時停止して次の行動や心を観察してみる。今どんな気持ちで、何をしようとしているのか。
次に我々の人生の「原則」と思われるものに従って行動するように努める。
よって我々が「原則」というものを常に考える必要もある。そしてそれを紙やのノートに記しておくことを勧めたい。
最後に言葉に気を付ける。なるべく主体的な言葉をつぶやいたり、声に出したりしてみる。
これに関しても一度どんな言葉が主体的なものか検証してみたいものだ。それに気づいたら、ノートやメモに買いみてる。
ただこれだけでは習慣は身につかないかもしれない。
ただこの中で最も大切であり、かつ試して価値のあるものは、「一度立ち止まる」つまり、何事にも冷静になって感情や衝動に巻き込まれずに、一時停止して状況や自分を客観視するということだ。コビィー氏の息子さんであり、「7つの習慣ティーンズ」を書いたショーン・コビィーさんも
「一時停止ボタン」を押しましょうと奨励している。われわれはあまりにもせっかちで、日々忙しく、そして追われる生活を強いられている。仕事だからすぐに判断しなければならないことはしょうがない。
ただ、感情や衝動に流されてしまうのはやはり「かなしい」。自分本位ではないという後悔も生じかねない。慌てず、かつ冷静に物事をしたい。そのためには「一時停止ボタン」は活用できる。
そこで
コビィー氏はこの主体的になるための方法として、我々に4つの理想的な行動の過程を示していることにも注目すべきだ。それは
自覚、良心、想像、意思という4つの作業である。
「自覚」は前にも述べたが、自分から離れて自分の考えや行動を観察するとうものだ。
「良心」は内なる声を聞き、善悪を判断するもの。
「想像」は新しい可能性を思い描くというもの。
「意思」は選ぶ意思といっていい。
これを意識しながら生活し、実践していく。最初はうまくいかないかもしれないが、筋トレのように意識してトレーニングだと思って継続していくことで、習慣化していくものだと思われる。
私はまずこの「自覚」を意識して生活するのはどうかと思っている。自分の行動を一つ一つ点検し自覚してみるのである。ある程度の時間を確保して、客観的に自分を見つめることに集中してみる。私は散歩のときや、仕事が終わって退社時に実験してみようと思っている。
特に散歩はすすめたい。
まとめ:人生の手綱を、自分の手に
今まで感情や衝動に反応してきた人生ならば、今後は「自覚」し、慎重に「選択」し、「原則」や「良心」をもとに判断を下せる生き方にパラダイム・シフトができればと思う。
まずは日々の生活でこれらのキーワードを意識しながら生きそして経験を積み、習慣化できたらと思っている。
これからしばらくは、この『7つの習慣』を軸に、自分自身の生き方を見直しながら、
その実践記録をこのブログで綴っていきたい。
同じように人生の節目を迎えている方、何か変えてみたいと感じている方の、
小さなヒントになればうれしい。
次回は、第二の習慣「目的を持って始める」について考えてみよう。
 | 完訳7つの習慣 30周年記念版 [ スティーブ・R.コヴィー ] 価格:2420円 |