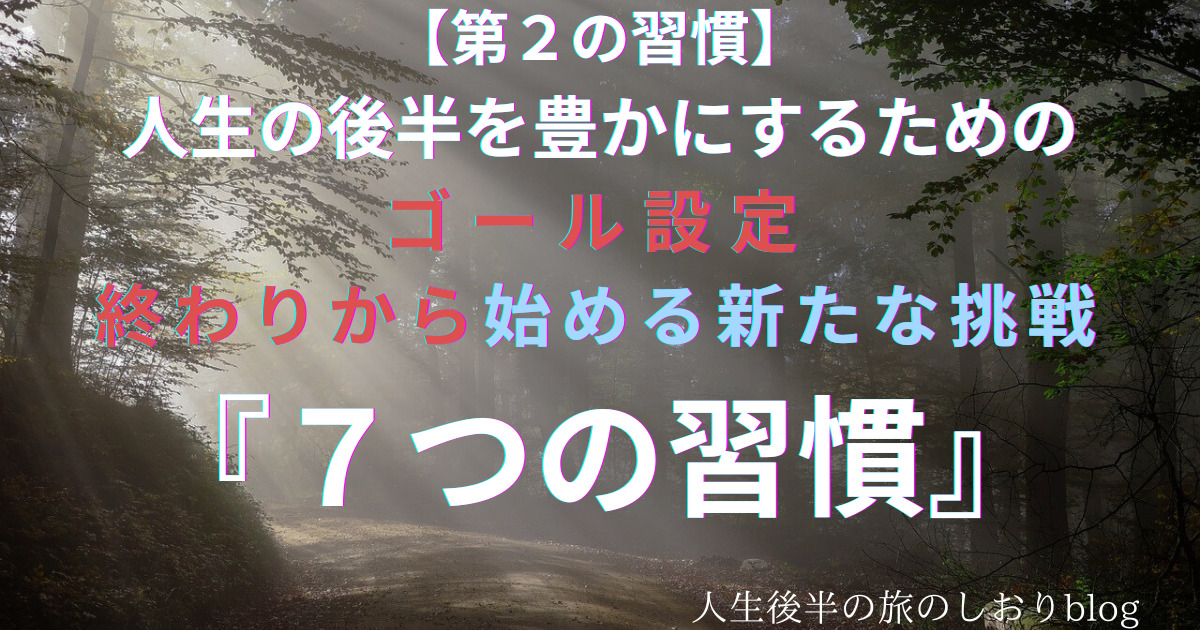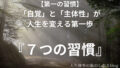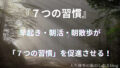さて、『七つの習慣』という世界的なベストセラーを読みながら、そして実践しつつ、今後の生き方の指針にしたいと思っているが、今回は「第2の習慣」である”終わりから思い描く”についてみていきたい。
そのためには「自覚」や「インサイド・アウト」そして「影響の輪」といった概念を理解する必要がある。詳しくは前回の記事を参考にしていだたきたい。簡単に整理すると、
「自覚」は自分自身を客観的に観察し、自らの感情の動きを見つめることである。
「インサイド・アウト」は外部の環境に左右されるのではなく、自分の意思や良心にしたがう内なる声にしたがって行動することであり、それによってアウトつまり、環境に影響を与えるということである。
「影響の輪」は「インサイド・アウト」に関連して、関心の輪に重きを置くのでなく、自分の力ではどうにもならない関心の輪よりも、自分の力でコントロールできる影響の範囲に意識を置く。というものだ。
我々は様々な出来事に出くわすが、そこから自由に「選択」できる。感情にただ流され左右されるのでなく、自由の意思を使って、原則や良心そして自覚をもって判断することで、自立した人間となることができる。つまり
主体的に生きる
これが、第一の習慣のポイントである。
そして自分の「原則」を持てと、著者スティーブン.R.コヴィー氏は説く。
そこから、次に人生の終わりから、今からの人生計画を立てようと述べている。これが「第二の習慣」となる。
本当の自分の人生を生きるためだ。
もう一度終わりから思い描く
コビィー氏は第二の習慣で「終わりから思い描く」ことを指示する。あなたがもし死後葬式の場でだれかが弔辞を読む。そのときに果たしてあなたはどんな弔辞を読まれたいか。
あなたの友人、家族、子供、配偶者、があなたについてどんな人であったかを述べる場面だ。「死」はだれにも訪れる。その「死」というゴールに向かって人は今日も生きている。
私の人生の「ゴール」は何なのか。果たして私はその「ゴール」を設定しているのか。いや単に毎日をその場しのぎで、ただ日々変わる私の都合や感情を中心として生きていないか。
私が成就したい人生のゴールを果たして持っているのか。毎日何となく生きていないだろうか。
50代になってふとこの書を手にして思う。もう一度私自身の人生の「ゴール」を決めてみたい。もう一度自分の人生の終わりが何であるか、考えてみる価値は十分にあると。
コヴィー氏は言う。人生は二度作られる。一つ目は第一の創造は知的創造。第二の創造は物的創造だと。いわゆる第一の創造で人生の設計図を作るということなのである。旅行に行く時も必ず行く先を決め、計画を綿密に立てるではないか。どうして自分の人生の計画を立てることをおろそかにするのであろうか。
またコヴィー氏は言う。人間だけに与えられている自覚、想像、良心を働かせよと。そうすることで自分の人生の脚本を自分で書くことができるのだと。
そこで我々の基本が「第一の習慣」であることが自明となる。その中でも「自覚」と「主体性」がキーワードだった。興味深いのはコヴィー氏は自分自身へのリーダーシップをも発揮せよと述べている。
自覚という能力を使って、主体的な心で、自分の人生のゴールを想像していく。これが「第二の習慣」となるのだろ解釈できる。
その時に心の奥底の価値観を見つめ、良心にしたがって、選択の自由から本当の自分の思いを見つめていく作業。次に彼は私自身の憲法つまり「ミッションステートメント」を作成しろ指導する。
自分のミッション。それは何か。
ミッションステートメント
まずはどんな人間になりたいのかといった「人格」
つぎに、
何をしたいのかといった「貢献」「功績」である。
このミッションステートメントを書くために、私は最初は箇条書きにしていた。しかし一度、原稿用紙に文章として書いてみた。これが非常にインスピレーションを呼び起こしよかった。
自分の思いを素直に書くことができた。と思う。これはとにかくまず書いてみることだ。
文章にしてみること。自分の手で紙に書いてみる。ジャーナリングみたいなものでいい。
そこから徐々に整理して箇条書きにしていくのがいいと私は思った。
この書では形式はそれほどこだわってはいない。人生のゴールはどういうものなのか。
私は何をしたいのか。何をもって人生を終わりたいのか。どんな貢献をしたいのか。そしてどんな功績を残したいのか。
そんなとき私は内村鑑三の「後世への最大の遺物」という本を思い出した。この書籍を一読するのもいいだろう。人生でわれわれは何を残すのか。このことが明確になることは非常に我々の人生を豊かにしてくれるはずだ。私は思う。
コヴィー氏はここで「あなたは何を中心に生きているのか」を問いている。
私の中心は何だったか。
ここでコヴィー氏は私に衝撃的な問いをする。あなたは何を中心に生きているか。
私は「私の意志」を中心に、「私の自覚」を中心に生きていたのだろうか。
もしかして、子供のご機嫌、配偶者のご機嫌、仕事や業務、学生の目の色、家族の目、知識や出世など。数えればきりがないのだが、正直こういった数々の要素が中心になっていたことは確かだった。
自分自身には非常に情けない思いもしたが、現実の自分を見つめる上で重要な気づきであったと思う。そこから私の価値観、原則を中心に変えていくことでいいのだ。本書では問う。
あなたの妻と今夜コンサートに行く約束をしていた。ところが突然、上司から呼ばれた。明朝9時に会議があるから今日は残業して明日に備えてほしいと。
あなたならどうするだろうか。ここで何を中心にしているかが、現れるというのである。そこでコヴィー氏は言う。
あなたが原則中心の生き方をしているなら、その場の感情のように、あなたの影響するさまざまな要因から一歩離れ、いくつかの選択肢を客観的に検討するだろうと。
つまり、仕事、家族、お金、代替案などの、全体のバランスをよく眺めて最善の解決策を見出す努力をするだろうと述べている。どんなメリットがあるか箇条書きにしてみた。
1)あなたが一番良いと思うことを主体的に選択している。
2)長期的な結果を予測できる原則に従って決めているから、自分の決断はもっとも効果的だと確信できている。
3)自分が選択したことだから、人生において多くの教訓と経験を得ることができる。
4)自立した人間としての決断だという点でにおいて相互依存の関係にも効果的だ。だれかに頼めることは頼むや明日の朝早く出社して残りを仕上げるなど。
ここで重要と思われるのは、
私の決断に納得している。
という点だと思う。だれかの意見やだれかの目を気にするのだはなく、自分の「自覚」という確固たる主体性から決断するのだ。
ゴールの見つけ方
ミッションステートメントの作る方法として、いくつか有益な方法が挙げれれている。
まずは一人の時間を持つということ。一晩で書けるものではない。緻密に分析し、表現も吟味する。そして何度も書き直して、最終的な文章に仕上げていくという。
次に脳全体を使うという。その中でも右脳を使うことで想像やイメージを作っていくという作業だ。
また決めてここまでで人生の最後だと期間(30日ほど)を決める。そして毎日日記をつけていくということを提示している。自分の人生にとって一番大切なものは何か。本当にやりたいことは何か。を真剣に考えるという時間をもつということだろう。
自分の向かうべき道はどこか。日々の生活を大切にしブレない自分を見出す。そうなのである。自分が見出す。普段から気づきてなかった私の役割を見出す作業がこの第二の習慣であり、ミッションステートメントの作成という聖なる作業だ。
今日は静かに部屋の中か、カフェか、それとも自然の中でか、自分の人生のゴールを考えて、紙に自由に書いてみてはどうだろうか。
遅咲きでもいい。焦らず私を見出す旅に出てみよう。
 | 完訳7つの習慣 30周年記念版 [ スティーブ・R.コヴィー ] 価格:2420円 |